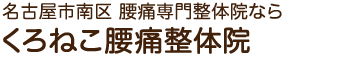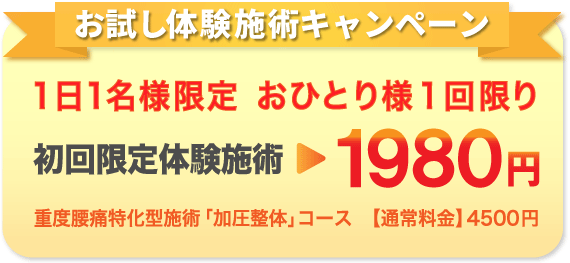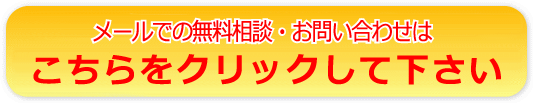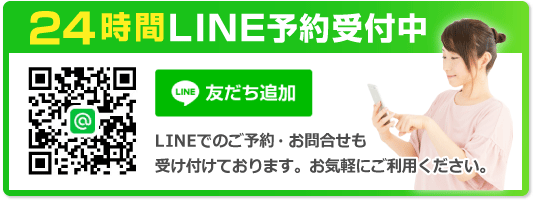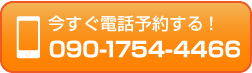名古屋 腰痛 治療法
2016-05-02 [記事URL]
名古屋 腰痛 治療法
1.運動療法
適度な運動によって腰まわりの筋肉、骨、軟骨、靭帯などの組織を強化して機能を向上させたり、組織の老化を遅らせたり、ストレスを解消したりすることで、腰痛の改善を図ります。 運動内容は主に、腰痛体操や柔軟体操・骨や筋肉を強化する筋力トレーニング・体力の向上や肥満の解消にも役立つ全身運動(ウォーキングや自転車こぎ)があります。
激しい腰痛がある時は、腰を動かさずに安静にしていることが原則です。しかしある程度痛みが和らいで動けるようになってきたら、無理のない範囲で積極的に体を動かしたほうが安静にするよりも治りが早いことが分かっています。安静にしすぎると回復を遅らせ、かえって状態を悪くしてしまうこともあります。
<運動による主な治療効果>
・筋力を高め、骨を丈夫にする
・筋肉や靭帯の柔軟性を高める
・関節の可動域を広げる
・組織の老化を遅らせる
・肥満やストレスを解消する
・体力がつき、免疫が高まって病気になりにくくなる
このように、運動によって腰を支える力が強くなるだけでなく、予防にもつながるような様々なメリットが得られます。
ここで簡単なストレッチ法を紹介します。
・前屈みで痛みが出る腰痛
→うつ伏せになり両手を肩幅につき下半身は力を抜いて床につけたまま上体を少し起こし、両肘を立てて体重を支えます。可能であれば両掌で体を支えさらに上半身を起こしていきます。
・体を後ろへ反らせると痛みが出る腰痛
→仰向けに寝て両ひざを抱え余裕があれば首を持ち上げて”おへそ”をのぞきこむようにすると、より効果が高まるほか背筋を伸ばすストレッチにもなります。その状態を数秒間維持していきます。
※ストレッチ時の注意点
・ぎっくり腰のように、急で激しい腰痛が見られる場合はストレッチをせず安静にしてください。
・体が沈み込むような柔らかい布団やマットの上ではなく、平らなところで行いましょう。
・強い痛みや不快感を感じない範囲でゆっくり伸ばしましょう。
・呼吸は止めずに行い、息を吐きながら伸ばし吸いながら元の姿勢に戻るのが基本です。
・体が温まっている時は筋肉が柔らかく関節の動きが良くなるので入浴後などに行うのがオススメです。
毎日少しずつでも良いのでストレッチを続けていきましょう。
2.薬物療法
痛みをコントロールするための薬物を服用する治療法です。炎症が激しく痛みが強かったり、安静にしていても痛みがとれない場合に、これらを和らげたり解消したりする目的で行われます。
<使用される主な薬剤>
・消炎鎮痛剤(痛み止め薬)
炎症を鎮めることで痛みを和らげる効果があり、最も良く使用される。通常は副作用の少ない非ステロイド性抗炎症薬が使われ、症状の重いケースに限り、鎮痛効果は大きいが副作用も大きいステロイド薬が使われる。
・筋弛緩剤:筋肉の緊張を和らげる
・抗うつ薬、抗てんかん薬、精神安定剤:ストレスからくる腰痛に効果がある
・血流改善薬、漢方薬、ビタミン剤など
痛みが激しい場合は、神経に麻酔薬や鎮痛薬を注射して神経の経路を一時的に遮断し、痛みを感じなくする神経ブロック療法も採られます。
薬の形態は、患部に直接貼り付けたり塗りつけるタイプの「外用薬」、口や肛門から服用する「内用薬(内服薬)・座薬」、患部に直接注入する「薬物注射」があります。
3.温熱療法
腰を温めることで血行を促進する治療法です。血行が良くなると、炎症や痛みの元となる化学物質や疲労物質が流れやすくなり、痛みが和らぎ回復が早まります。また、筋肉が柔らかくなり関節の動きも良くなって、負荷や衝撃を吸収・分散する働きが強まり、腰の負担が減ります。からだの動きが良くなってケガもしにくくなります。医療機関では電気・超音波を使った専用機器やホットパックを使用します。家庭でも、入浴、カイロ、腹巻き、サポーターなど、様々な方法で手軽に患部を温めることができます。
※ぎっくり腰などの急性腰痛症発症した直後は温めると悪化する恐れがあるのでその場合は冷却しましょう。
4.装具療法
腰の保護、固定、動きの安定を目的とした器具を腰まわりに取り付けることで、腰の負担や痛みを軽減する治療法です。
装具とは身体機能を補うために体に装着する器具のことで、腰用のコルセットやサポーターなどがあります。
<装具の効果>
・外部からの衝撃を和らげ、腰の筋肉や骨を保護する
・腰を適度に固定して、腰によくない不適切な動きや姿勢を制限する
・良い姿勢を保つ(外した後も姿勢が良くなりやすい)
・背骨のゆがみを矯正する
・安心感が得られる
→腰痛がひどい人の場合、ちょっとした動作で腰に激しい痛みを感じるため、常に姿勢や動作に気を使い神経をすり減らしながら生活しなければなりませんが、装具を付けていれば腰の動きが制限されるため、そうした気疲れが少なくなり気持ちが楽になります。
<過度の使用は逆効果にも>
装具をつけると腰が楽になるのは、装具が腰の筋肉の代わりに体を支えてくれるからです。筋肉は使われないと細く弱くなっていきます。装具に頼りすぎて漫然と長い期間使い続けると、腰を支える力が弱くなり、装具を外した後に痛みはかえって悪化する場合もあります。
6ヶ月程度の装着では大きな影響はないとも言われていますが、装具への依存心を強めすぎないためにも、ある程度痛みが和らいできたら装具は外し、筋肉を鍛える運動療法などの治療法に移行していきましょう。
コルセット治療は”急で激しい痛み”が見られる腰痛の急性期のみに行うことが合理的です。どうしても使い続けたい場合は、腰巻きのような薄手のコルセットをつけている程度なら問題ないです。
5.神経ブロック療法
腰痛の中でも椎間板ヘルニアなど腰痛に伴い下肢の痛みが強く、服用したお薬で効果が得られない場合に、選択させることがある「神経ブロック療法」。痛みが強すぎたり、痛みが長く続いてしまうと、その痛みにより、体を活動的な状態にする交感神経系が緊張してしまい、痛みを強めてしまう恐れがあります。 連続した強い痛みは、予想以上に腰痛の回復を遅らせる可能性があるため、モトとなる神経に局所麻酔を用いて、痛みの伝達をブロックし、続く痛みの悪循環を遮断します。神経ブロック療法の中でも種類があり、神経に直接注射をせずに、神経の周囲に麻酔薬を注射する方法もあります。
6.手術療法
腰痛の治療の基本は上記で紹介した保存的療法です。一定期間は保存療法を行い、症状が改善するかどうか様子を見ますが以下のようなケースにおいては手術による治療も検討されます。
・保存的療法を一定期間行なっても症状が改善しない、または悪化している
・腰痛やそれに伴う症状によって日常生活に支障が出ている:激しい腰痛の継続、足の強いしびれ、マヒ、筋力の著しい低下、排尿・排便障害など
・すぐに治療を行わないと障害や後遺症が残ったり、生命に関わる病気が発症している:骨の悪性腫瘍(がん)や一部の内蔵の病気など
ひと昔前までは、手術といえばメスで患部を大きく切除して行うような大がかりなものが主でした。しかし近年の医療技術の向上により、現在では内視鏡を使った体の負担の少ない手術や、手術以外の治療法も併用した効率的な方法が考案され、同じ症状に対する手術法の選択肢が増えてきました。
各手術法には長所と短所があり、どの方法を実施するかは、腰の状態、患者の体力や年齢、本人の希望、普段の生活環境などを考慮して決定します。
名古屋 緑区 腰痛
2016-04-25 [記事URL]
腰痛予防についてお話します!!
1.姿勢を正しくする
毎日の何気ない姿勢や動作が慢性的な腰痛の原因になったり、急性の腰痛を引き起こす引き金になることがあります。正しい立ち方や座り方を心がけて、腰痛を予防していきましょう。
◎正しい立ち方:正しい立ち方は軽くあごを引く・肩の力を抜く・腹筋に力を入れる・背筋、膝をキチンと伸ばした姿勢です。真横から見た場合、耳から肩・股関節・膝・くるぶしを結んだ線が直線で描かれていることが理想的です。
簡単なチェック方法としては、背中を壁にあてて立ち、後頭部・背中・お尻・かかとが壁につく状態が、正しい姿勢の目安になります。
◎正しい歩き方:正しい歩き方は前に出した足のかかとから着地し、足の親指で地面を蹴り、後ろ足は最後につま先が離れるのが基本です。また、つま先を軽く開き、直線上を歩くように意識しましょう。背中を丸めて歩いたり、からだを反らせすぎると腰に負担がかかるので、注意してください。
◎正しい座り方:椅子に座る場合はお尻が背もたれに密着するように、深く腰かけてください。軽くあごを引き、背筋を伸ばしてお腹を軽く引き締めます。ひざがお尻よりわずかに高くなるのが理想です。イスが高すぎる場合は、足を台にのせるなどして、ひざの位置を調節しましょう。
床に座る場合でもっとも腰に負担がかからないのは、背筋を伸ばして座る正座です。ただし、正座はひざに負担をかけるため、膝が痛い場合は避けください。
あぐらや体育座り、 足を投げ出して座る姿勢は、腰に負担をかけます。
※同じ姿勢を長く続けるのは、腰や背中に負担がかかりますので、やめましょう。
脚を組むと力のバランスが崩れ、特定の筋肉を緊張をさせて、歪みが起こることがあります。
◎正しい寝かた:正しい寝かたはリラックスできる姿勢が基本ですが、うつ伏せで寝ることだけは避けましょう。痛みがあるときは、横向きでやや前かがみの姿勢で寝るのが良いとされています。仰向けで寝る場合は、ひざの下に枕などを置いて寝ると、腰の負担が軽くなります。また、寝具にも気を使いましょう。柔らかいベッドや高すぎる枕は、腰が落ち込んで反りすぎてしまうため、避けてください。
2.適度な運動を心がける
移動で乗り物に頼ることが多い現代人は、運動不足に陥りがちです。腰痛予防のスポーツとしては、腰に負担がかからない水泳がおすすめです。反対に、ゴルフ、テニスなどのからだをひねるスポーツは腰痛の原因になることがあるため、運動前にきちんと準備運動を行いましょう。また、過度の仕事やスポーツは、背骨を支える筋肉が疲れ果てて、椎間板ヘルニアなどの原因にもなります。運動は適度に行うよう心がけて、ストレッチやマッサージなどでからだをほぐすようにしましょう。
◎背中から臀部・大腿裏を伸ばす:仰向けに寝て両手で両ひざを抱え、頭を中に入れるように背中を丸め、背中からお尻、太腿の裏側を伸ばすように意識してください。
◎わき腹を伸ばす:柱や壁の横で背すじを伸ばして真っ直ぐ立ちます。両手を柱や壁に置き、あるいはつかまって、腰を手と反対側に押し出すようにして伸ばしましょう。
◎下肢後面を伸ばす:両足を交差させて正しい姿勢で立ちます。この状態で、ひざが曲がらないように気をつけながら、前屈を行います。
※すべて痛みのない範囲で気持ちよく伸ばしましょう。
3.痩せすぎ・肥満に注意
太っている人は、標準体重の人よりも重い荷物を背負っていることと同じになるため、腰痛を起こしやすくなります。また、運動不足に陥りやすく、筋力の低下により、背骨を支える機能が低下する事により腰痛が起こります。肥満体質の人は、減量によって腰痛が改善されることが少なくないため、ダイエットに挑戦してみましょう。
痩せすぎも注意が必要です。痩せすぎは筋力の低下を招き、背骨を支える腹筋が弱くなります。腰痛を防ぐためには、適度な筋肉をつけておきましょう。
4.靴選びに注意
自分の足に合わない靴を無理に履いていると、腰痛を起こす原因になります。特に、女性はハイヒールに注意です。ハイヒールはお尻を突き出す姿勢になるため、腰に大きな負担をかけます。
5.ストレスをためない
ストレスによる心因性の腰痛もあるため、注意が必要です。アロマテラピーなどで心をリラックスさせるのも良いですし、好きな音楽を聴いたりするのも良いでしょう。
自分がしっかりリラックスできる環境を整えましょう。
6.同じ姿勢を続けない
立ちっぱなしや車の運転など、長時間同じ姿勢を続けると、腰に大きな負担をかけます。時間を決めて歩いたり、イスから立ち上がったり、伸びをしたり軽いストレッチをして腰痛を予防しましょう。
名古屋 天白区 腰痛
2016-04-25 [記事URL]
腰痛の種類
≪加齢が原因のもの≫
1.変形性脊椎症
・症状:腰に鈍い痛みや強張りを感じ立ち上がるときや寝返りで症状が強くあらわれることが多く、最初が最も痛く徐々に痛みが緩和していくことが特徴的です。
・原因:椎間板の水分が減少して弾力がなくなることで、脊椎が変形して周囲の神経を刺激することが原因。
2.脊椎骨粗鬆症
・症状:腰から背中にかけて痛みを感じることが多く、なかなか痛みが取れないことが特徴的です。重症になると背が低くなったり丸く曲がることがあります。
・原因:骨の成分が抜けて骨量が減りスカスカの状態になるため、小さな力で圧迫骨折を起こします。
3.椎間関節症
・症状:朝の起床時に最も強く症状があらわれなかなか起き上がることが出来ず、起き上がって活動を始めると徐々に痛みを感じなくなります。
・原因:腰椎の関節の炎症によるもの。
≪筋肉や神経が原因のもの≫
1.腰痛症
・症状:中腰でものを持ち上げようとしたときに突然発症するものはぎっくり腰と呼ばれます。腰の痛みがあってもレントゲン写真からは異常の原因を断定することが 出来ません。前にかがんだり寒いところに長時間いるときに、症状が強く表われることが特徴です。重い痛みが続き、慢性化する場合もあります。
・原因:関節の筋肉や神経に強い負荷がかかったり、過度の緊張や疲労によって起こります。運動不足や肥満、ストレスによる血行不良で筋肉疲労を起こすこともあります。
≪椎間板が原因のもの≫
1.椎間板ヘルニア
・症状:腰から足の爪先にかけて、痺れや痛みが表われます。痛みで真っすぐに立てないことも多く、重症になると排尿障害を起こします。
・原因:弾力を失った椎間板の髄核が外に飛びだして、神経を圧迫することで起こります。加齢による場合と、運動や労働で過度の負荷が掛かった場合が考えられます。
≪脊椎が原因のもの≫
1.脊椎狭窄症
・症状:立ち上がって腰を伸ばすと痛みを感じます。長く歩くと腰から足の裏にかけて痺れや痛みの症状があらわれ、歩けなくなることもあります。(間欠跛行)
・原因:脊柱管の内径が狭まり、中を通っている神経や血管を圧迫することによって起こります。
2.脊椎分離症
・症状:腰に痛みを感じ、しばしば下肢に痛みや痺れが表われます。同じ姿勢を長く続けていると症状が強く表われる特徴があります。
・原因:椎弓(腰椎の後部)が骨折(断裂)して脊柱が不安定になるため起こる。
3.脊椎すべり症
・症状:脊椎分離症と同様の痛みで、下肢にも痺れや痛みが出てきます。
・原因:椎骨の一部がズレて腹側に移動したため、神経を圧迫され発症します。
・急性腰痛...突然腰に激痛が走り、その場から動けなくなるもの。ぎっくり腰と呼ばれるものは、検査をしても椎間板や骨格組織にも異常が認められず神経痛も発症しません。目立ったものがないにも関わらず、腰痛の症状がある場合には、ぎっくり腰や急性腰痛、椎間捻挫などの症状名がつけられることになります。
急性腰痛の中でもぎっくり腰の原因となるものを3つ紹介します。
1.筋肉疲労によるもの
まず挙げられるのが、筋肉の慢性疲労です。ぎっくり腰は突然起こりますが、症状としていきなり表れるだけで、ゆっくりとその原因となるものは進行しているのです。
中腰で荷物を持上げようとした瞬間に激痛が走ったり、よろめいてちょっと片足を勢いよくついてしまった瞬間などにぎっくり腰になりやすいですが、日常の中で同じ動作をしても平気だったのに、ある瞬間にぎっくり腰になってしまうのです。
これは、少しずつ溜め込んだ筋肉疲労が、あるとき負荷の許容量を超えてしまい、腰痛として発症してしまったと言えるでしょう。日常生活を送る中で、筋肉疲労は必ず起こります。
それを回復するメカニズムを持ち合わせていますが、睡眠不足や栄養バランスが取れていなかったり、運動不足や座りっぱなしの仕事を続けるなどしていると、筋肉疲労が回復することなく徐々に蓄積されていき、やがて腰痛を招いてしまうことになるのです。
2.いきなりの過負荷によるもの
若い人やスポーツ選手に多いぎっくり腰の原因の1つで、高いところから飛び降りた着地の瞬間や、勢いよく振り返った瞬間、横になっていて勢いよく起き上がったときなど、止まっている状態からいきなり動いたときや、動きの急激な切り替えの時に、腰にいきなりの過負荷がかかり、ぎっくり腰を起こしてしまいます。
3.骨格の歪みによるもの
ぎっくり腰になる原因の1つに、骨格の歪みもあげることができます。私たちの日常を振り返ってみると、立ちっぱなしの仕事や座りっぱなしの仕事に就いていると、長時間、限られた姿勢でいることが多いと思います。こうすることで、身体の柔軟性が失われていき、同じ骨格や筋肉だけを使うことになってしまいます。
使われている筋肉には負荷がかかり、使われていない筋肉は少しずつ緩んでいきます。こうしたことが筋力のアンバランスを生み出し、骨格の歪みを招いてしまいます。
歪んだ骨格は左右のアンバランスを生み出し、その周囲の筋肉への負荷に変わります。身体のバランスをとろうとする代わりの筋肉にも徐々に筋肉疲労が蓄積され、やがて腰痛につながるのです。
名古屋市南区 急性腰痛症の予防法
2016-04-20 [記事URL]
急性腰痛症とは、通称ぎっくり腰と呼ばれる症状です。
ここでは、突然襲い掛かる急性腰痛症の対処法や予防法などを紹介します。
【急性腰痛症になったら】
急性腰痛症は、突然の腰の痛みで歩く事も立つ事も出来なくなります。
その為、周りに人がまったくいない場合に急性腰痛症になってしまうと、どうする事も出来ずにただパニックに陥る事もあるので、この機会に正しい対処法を覚えておくといいでしょう。
まず急性腰痛症が襲ったら、体を無理に動かすのは禁物です。
あまりの痛さにパニックになる事もありますが、まずは体を安静に保ち、楽な姿勢になりましょう。
もっとも楽な姿勢は、横になり、関節、ひざを曲げて、海老のような姿勢をとる事です。
急性腰痛症は、筋肉に炎症が起こっている状態なので、まずは患部を冷やし、炎症を抑えるようにしましょう。
ただし、冷やしすぎは禁物です。
肌に直接触れないよう氷嚢等をタオルで包んで、1回10分から15分程度冷やします。
炎症が治まってきたら、今度は、患部を温め、血液の循環を回復させてください。
急性腰痛症で安静はとても重要ですが、長すぎる安静は、逆効果になる事もあるので、3日から4日程度で少しずつ体を動かすのがお勧めです。
体が少しずつ動かせるまで回復したら、再発のリスクを軽減するためにも一日も早く接骨院で正しい処置を受けるようにしましょう。
万が一2,3日安静にしても、痛みがまったく改善しない、余計に痛みが悪化していると感じる場合は、他の疾患も疑い、病院を受診することをお勧めします。
急性腰痛症を引き起こす病気には、椎間板ヘルニア、脊椎すべり症、腫瘍などの疾患があります。
また高齢者の場合は、骨そのものが折れている可能性もあるので、早めに詳しい検査を受けるようにしてください。
【急性腰痛症を予防する方法は?】
急性腰痛症は、普段から心がけで予防できます。
・血行不良対策
血液の循環が悪くなると筋肉に疲労から急性腰痛症の発症のリスクを高めます。
その為、冷え性や肥満、窮屈な下着、など血管を圧迫するような状況を避けるのが急性腰痛症の予防の一つです。
冷え性や肥満による血行不良については、半身浴や食事の改善、適度な運動などで、十分対応できます。
・骨盤矯正
骨盤のゆがみは、体全体のゆがみにつながり、腰や股関節などある一定の部分に負担が偏ってしまいます。
そこへさまざまな要因が加わると急性腰痛症になりやすい傾向にあるので、骨盤矯正は必要です。
骨盤矯正は、接骨院等の得意分野で、定期的に施術を受けることで本来のS字カーブを描く正しい姿勢をキープできます。
・動作の意識
急性腰痛症の直接の原因となる動作は、特に重要です。
荷物を持ち上げるとき、眠るとき、など日常生活の何気ない行動の一つ一つが腰に大きな負担をかけています。
年齢を重ねると特に、これらの動作が不十分で、腰だけに負担をかけて行動している方が多いのが現状です。
例えば、下に置かれている荷物を持ち上げるときは、体全体で持ち上げるように心がけましょう。
手を伸ばし、腰だけで持ち上げようとすると急性腰痛症になる事が多いので、注意をしてください。
名古屋市南区 急性腰痛症の予防法なら、「くろねこ腰痛整体院」にお任せください。
名古屋 南区 背中の痛み
2016-04-19 [記事URL]
背中の痛みの原因は運動による筋肉痛や姿勢の悪さなどが関係していますが、原因がはっきりしない場合には注意が必要です。
背中と内臓には密接な関係があり、また右側、左側の痛みによっても原因が変わることがあります。
痛みの原因は、筋肉疲労から内臓の病気までいろいろなものがあります。
まず背中の痛みの原因としてあげられるのは、背中の筋肉が緊張したり、負荷がかかりすぎて疲労する背中のこりや筋肉痛です。
痛みの度合いや症状もさまざまで、すぐに改善するものから長期間にわたる慢性的なものまであります。
骨がずれてしまったり歪みによっても、背中の痛みが起きます。
背骨や首の骨が変形して痛みを感じたり、背骨の骨折などで痛くなることもあります。背中以外の部分に大きな衝撃を受けて、打撲や捻挫をして体
全体の歪みから背中の歪みにつながり痛くなることもあります。
それから、意外に思われるかもしれませんが、内臓疲労や内臓疾患が原因で背中の痛みが生じることもあります。
呼吸器系の疾患から循環器系、腎臓、消化器系、子宮疾患まで多岐にわたります。
その他の原因として、寝違えたり筋を違えたり、事故によるむち打ち症などで首が痛い時に首から背中の上の部分が痛むことがあります。
痛みが感じられる部位によって起こる原因や疑われる病気は異なってきます。
今回は背中の真ん中・右側・左側・首から胸の痛みそれぞれの部位から引き起こす病気を紹介しています。
1.背中上部・首・肩にかけての痛み
≪主な症状≫
・首、肩、背中にかけて違和感、不快感、だるさ、しびれ、鈍痛などを感じる
・首、肩、背中の辺りがずっしりと重く感じる
・肩~首すじがガチガチにこわばっている、または張っている
・肩から腕にかけてしびれがある
≪その他の症状≫
筋肉疲労による筋肉の硬化、コリや痛みがあり、一般的な肩こり・腰痛などに分類されます。
2.背中上部・肩・腕・首から肩甲骨にかけての痛み(上肢のしびれ 胸郭出口症候群)
≪主な症状≫
・上肢のしびれ
・肩や腕、肩甲骨周囲の痛み
・前腕尺側と手の小指側に沿ってうずく
≪その他の症状≫
前腕尺側と手の小指側に沿ってうずくような、ときには刺すような痛み・しびれ感・ビリビリ感などの感覚障害に加え、手の握力低下と細かい動作がしにくいなどの運動麻痺の症状があります。
手指の運動障害や握力低下のある例では、手内筋の萎縮により手の甲の骨の間がへこみ、手のひらの小指球筋が痩せてきます。
鎖骨下動脈が圧迫されると、上肢の血行が悪くなって腕は白っぽくなり、痛みが生じます。鎖骨下静脈が圧迫されると、手・腕は静脈血のもどりが悪くなり青紫色になります。
3.胸の痛みがあり背骨を後ろから押されたような圧迫感がある(胸椎前方変位)
≪主な症状≫
・胸の痛み(特に深呼吸時)
・背骨を後ろから押されたような圧迫感
・上向きで寝れない
≪その他の症状≫
胸椎前方変位(背中のほうにある緩いカーブが前方へ出てしまうこと)がみられる。
ダンサーなどの柔軟性を必要とする仕事の人に多く見られます。
原因としては上半身を後ろに反らせた姿勢を多くとるなど胸椎を前方に反らせるような圧力が継続的にかかることによります。
4.背中の右側が痛い(肝炎・急性肝炎)
≪主な症状≫
・背中の右側が痛い
・全身がだるい(全身倦怠感)
・発熱、食欲不振、吐き気、嘔吐
・黄疸
≪その他の症状≫
発症の仕方や症状の経過から大きく3つに分類され、突然発症し一過性の急肝炎、6か月以上の症状のおさまらない慢性肝炎(数値が正常に戻らない)、急性肝炎のうち1週間から10日で死に至ることが多い劇症肝炎があります。
5.背中の右側が痛い、疲れやすい(肝臓がん)
≪主な症状≫
・腹部のしこり
・圧迫感
・腹部の張り感
≪その他の症状≫
肝硬変に伴う症状として食欲不振・ダルさ・微熱・便秘・下痢・貧血・むくみ・皮下出血などがあります。
肝硬変が進行すると腹水が出現したりアンモニアが代謝されずに貯蓄することによる肝性脳症という意識障害を起こすこともあります。
6.右肩から右背中にかけて響くような痛み(胆石症)
≪主な症状≫
・みぞおちから右上腹部にかけて突発的な激しい痛み
・吐き気、嘔吐
・黄疸
・尿の色が濃くなる
≪その他の症状≫
上腹部の違和感、腹部膨満感、背中や右肩なコリや痛みを伴うことがある。
7.右肩や背中、みぞおちや肋骨下あたりの痛み(胆嚢炎)
≪主な症状≫
・発作的な痛みで激しく長く続く
・腰痛
・高熱、吐き気、嘔吐
・黄疸
≪その他の症状≫
持続した炎症が続くと右腹腔内での癒着が出現することがある。
8.背中の右側の痛み、発熱(胆嚢がん、胆管がん)
≪主な症状≫
・上腹部の痛み
・黄疸
・右上の腹部にしこり
≪その他の症状≫
全身倦怠感、腹痛、発熱、食欲不振、体重減少など
9.背中の左側から左下の痛み(膵炎)
≪主な症状≫
・みぞおちから左脇腹上部にかけての痛み
・吐き気、嘔吐、下痢、便秘
≪その他の症状≫
痛みは軽いものからじっとしていられないほどの激痛まであり様々です。
特に油分の多い食事をした後やアルコールを多く飲んだ後に起こることが多い。
膝を曲げて腹ばいになると痛みが和らぐことがあります。
10.背中の左側から左下の痛み(膵臓がん)
≪主な症状≫
・みぞおちに鈍痛
・胃のあたりや背中が重苦しい
・体重の減少
・黄疸
≪その他の症状≫
体が痒くなったり、尿の色が濃くなったりします。黄疸が出現すると膵頭部にがんができて胆管が詰まってしまった時に起こります。
膵臓がんになると糖尿病を発症したり血糖のコントロールが悪くなったりすることがあります。
11.背中の左側から左下の痛み、腹部の痛み(胃炎、神経性胃炎)
≪主な症状≫
・胃のあたりに不快感や痛みがある
・胃のむかつきや嘔吐(吐血することも)
・体がだるい、食欲不振、頭痛
≪その他の症状≫
空腹時や夜間の胸やけ、食後のむかつきは慢性胃炎に特有のものではなく、胃潰瘍・胃がんなどでも同様の症状がみられます。
症状が全く見られない場合もあります。
12.背中の左側から左下の痛み、胃のあたりの痛み(胃潰瘍、十二指腸潰瘍)
≪主な症状≫
・みぞおち、胃の痛み
・出血して吐血
・穿孔
≪その他の症状≫
腹痛がみられます。前兆として腹部不快、軽い腹痛を示すことがまれにありますが、通常は急激な腹痛が突発的に起こります。
痛みは持続し、初めは限られた部位だけですが、次第に腹部全体に及びます。
そのほかの症状として吐き気・嘔吐、発熱、頻脈がみられます。病気が進行している場合には、脱水・ショック状態に陥ることもあります。
13.背中の左側から左下の痛み、腹部の痛み(胃がん)
≪主な症状≫
・上腹部の痛み
・漫然と続く胃の不快感
・食欲不振
・吐き気が続く
・胸のもたれ
・黒色の便が出る(胃がん初期症状)
≪その他の症状≫
げっぷの頻発、漠然とした不快感といった症状が出たり消えたりするようになります。
このような胃がんに共通してみられる症状に加えて、がんが食道につながる胃の入り口で大きくなった場合は、食物が噴門近くで停滞し、つかえ感
胸やけなどの症状が出現します。
14.背中の左側から左下の痛み、みぞおちから左胸にかけての痛み (狭心症)
≪主な症状≫
・胸の中央部が締め付けられる
・押しつけられているような圧迫感がある
・胸からのドにかけての痛み
・左肩、左腕などの痛み
≪その他の症状≫
痛みは左肩・腕や顎までひろがり、みぞおちに胃の痛みのように感じられることもあります。息切れすることもあります。
痛みの場所はあまりはっきりしないのが一般的です。「この一点が痛い」と指で示せるような場合は心配ないと思っていいでしょう。
症状の持続時間は数十秒から数分で、もっと短い場合は心配ないといってよいでしょう。
15.背中の左側から左下の痛み、胸の前部に痛み(心筋梗塞)
≪主な症状≫
・強い胸部の痛みや苦悶感が生じ15分以上持続する
・顔面蒼白
・冷や汗
・除脈
・血圧の低下
≪その他の症状≫
局所の貧血が解消されなければ痛みや苦悶感が数時間以上続く。
脈拍の上昇などを伴い、意識不明に陥ることもある。
この他にも背骨(脊椎)の変形などが原因で起こるものもあります。
1.脊椎後湾症(円背、猫背、亀背)≪主な症状≫
・かなりの猫背である ・腰痛がある
2.脊椎側弯症≪主な症状≫
・裸になって背中を見た時に、通常は真っ直ぐなはずの背骨が横に曲がっている
・肩やウエストの高さが左右で違う ・腰痛がある
3.胸椎前方変位≪主な症状≫
・胸の痛みがある(特に深呼吸をした時に激しく痛む)
・背骨を後方より押されたような圧迫感がある ・上向きで寝れない
4.骨粗しょう症
≪主な症状≫
・腰や背中に長くしつこく続く痛みがある
・以前より背中や腰が丸まってきた(曲がってきた)
≪その他の特徴≫
・閉経後の50歳以上の女性に圧倒的に多く、高齢になるほど発症しやすい。男性にはほとんどみられない
5.強直性脊椎炎≪主な症状≫
・腰や背中が重たく感じたり、固くこわばって動かしにくい。 ・または筋肉痛のような痛みがある
≪その他の特徴≫
・日本の患者数は400~500名で珍しい病気。患者のほとんどが10~20代の若者で、男性に非常に多い(女性の5~10倍)
6.化膿性脊椎炎≪主な症状≫
・背中や腰に急で激しい痛みがある。 ・患部を叩くと強く痛み、安静にしていても痛む
≪その他の特徴≫
・寒気や発熱など風邪のような症状が出ることもある
7.脊椎カリエス≪主な症状≫
・腰や背中の中心に鈍い痛みやコリ、動きの違和感を感じる
・全身のだるさや食欲不振、微熱など
≪主な原因≫
・結核菌による病気で、結核患者からの感染、過去に結核にかかった際に残ったウイルスなど
◎日常生活で気を付ける事
1.姿勢に気を付ける
同じ姿勢で長く立ち仕事する調理台などは、前屈みにならないよう補助台を置くなどして自分に合った高さに調節する工夫をしましょう。
また、パソコンなどのデスクワークで座り続けることの多い人はいすに深く座り、背骨を伸ばし、膝、足首が90度になるように高さを調節するなど、
姿勢に気を配りましょう。また、寝るときの高すぎる枕も背中の筋肉に負担をかける原因になりますので、注意しましょう。
2.肩と背中の筋肉を鍛える
日頃から、腹筋と背筋を鍛える運動を心がけましょう。仰向けに寝た状態で腰の下にたたんだタオルを当て、自転車を漕ぐように空中で足を回す動
作は、腹筋と背筋を同時に鍛えることができます。痛みが強いときは決して無理をしないことが大切です。
3.ストレッチをする
立ち仕事や座り仕事が続くと、背中の筋肉が緊張してこりを感じます。手を上にあげて体を伸ばしたり、肩や首を大きく回すなど、簡単なストレッチ
を数時間ごとに行うことで、筋肉の緊張がやわらぐので続けてみましょう。
4.ぬるめのお風呂にゆっくりつかる
40℃前後のぬるめのお湯にゆっくりとつかることで、血行を促進して背中の筋肉の疲れやこりを改善することができます。入浴中に背中を伸ばした
りすると、さらに血行改善の効果があります。
名古屋 背中の痛み
2016-04-19 [記事URL]
背中の痛みの原因は運動による筋肉痛や姿勢の悪さなどが関係していますが、原因がはっきりしない場合には注意が必要です。
背中と内臓には密接な関係があり、また右側、左側の痛みによっても原因が変わることがあります。
痛みの原因は、筋肉疲労から内臓の病気までいろいろなものがあります。
まず背中の痛みの原因としてあげられるのは、背中の筋肉が緊張したり、負荷がかかりすぎて疲労する背中のこりや筋肉痛です。
痛みの度合いや症状もさまざまで、すぐに改善するものから長期間にわたる慢性的なものまであります。
骨がずれてしまったり歪みによっても、背中の痛みが起きます。
背骨や首の骨が変形して痛みを感じたり、背骨の骨折などで痛くなることもあります。背中以外の部分に大きな衝撃を受けて、打撲や捻挫をして体
全体の歪みから背中の歪みにつながり痛くなることもあります。
それから、意外に思われるかもしれませんが、内臓疲労や内臓疾患が原因で背中の痛みが生じることもあります。
呼吸器系の疾患から循環器系、腎臓、消化器系、子宮疾患まで多岐にわたります。
その他の原因として、寝違えたり筋を違えたり、事故によるむち打ち症などで首が痛い時に首から背中の上の部分が痛むことがあります。
痛みが感じられる部位によって起こる原因や疑われる病気は異なってきます。
今回は背中の真ん中・右側・左側・首から胸の痛みそれぞれの部位から引き起こす病気を紹介しています。
1.背中上部・首・肩にかけての痛み
≪主な症状≫
・首、肩、背中にかけて違和感、不快感、だるさ、しびれ、鈍痛などを感じる
・首、肩、背中の辺りがずっしりと重く感じる
・肩~首すじがガチガチにこわばっている、または張っている
・肩から腕にかけてしびれがある
≪その他の症状≫
筋肉疲労による筋肉の硬化、コリや痛みがあり、一般的な肩こり・腰痛などに分類されます。
2.背中上部・肩・腕・首から肩甲骨にかけての痛み(上肢のしびれ 胸郭出口症候群)
≪主な症状≫
・上肢のしびれ
・肩や腕、肩甲骨周囲の痛み
・前腕尺側と手の小指側に沿ってうずく
≪その他の症状≫
前腕尺側と手の小指側に沿ってうずくような、ときには刺すような痛みと、しびれ感、ビリビリ感などの感覚障害に加え、手の握力低下と細かい動作がしにくいなどの運動麻痺の症状があります。
手指の運動障害や握力低下のある例では、手内筋の萎縮(いしゅく)により手の甲の骨の間がへこみ、手のひらの小指側のもりあがり(小指球筋)がやせてきます。
鎖骨下動脈が圧迫されると、上肢の血行が悪くなって腕は白っぽくなり、痛みが生じます。鎖骨下静脈が圧迫されると、手・腕は静脈血のもどりが悪くなり青紫色になります。
名古屋 猫背 姿勢 パート2
2016-04-18 [記事URL]
猫背とは背中が丸く曲がり顔が前に突きだした姿勢のことを言います。猫背というのは俗称であり医学的には「脊柱後湾症」と言います。
元々人の背骨はまっすぐなわけではなく、首から腰に掛けてS字を描くように曲がっているのが通常です。
これは、体重の約10%と言われる頭の重さを支えるためであり、S字を描くことで頭の重さを首・肩・背中・腰に分散させているのです。
猫背になると頭の重さが首や肩に掛かるようになり、ひどい肩こりや頭痛に悩まされるようになります。また、常に背中が丸まっている状態なため、内蔵を圧迫し血行不良となって胃腸の不調や手足のしびれなどが起こることもあります。さらに、冷え症やむくみによって太りやすくなるなど、猫背が引き起こす症状は実に様々にあります。
どれも一見猫背とは全く無関係に思えますが、これらの症状に長年悩み、あらゆる方法を行っても改善する気配がない場合は、猫背が原因で起こっているのかも知れません。
猫背の認識は「背中が丸まっている」方が猫背だと認識するかと思いますが、実はこの背中の丸まる原因によって猫背の種類が分別されます。
今回は大きく3つのタイプに分けていきます。
1.そり腰により骨盤前傾型猫背タイプ
この猫背のタイプは骨盤が通常より過前湾している為、身体のバランスを取ろうとする際に首だけ前に出してしまい猫背の様な姿勢になります。また、腰が反り過ぎている為に腰痛にもなりやすい傾向があります。
2.一般的な猫背のタイプ
まず一般的に多い猫背タイプですが、背中の中央部分だけが丸まる「猫背」です。
背中にある姿勢を維持する筋肉が弱く常に背中を丸めるようになる為この様な姿勢になってしまいます。常にこの様な姿勢をしていると姿勢を維持する筋肉は普段から使わないことになるので余計筋力が低下します。仰向けで寝るのが辛くなりうつ伏せや横になって寝ることが多くなります。
3.骨盤後傾型猫背タイプ
最後は『骨盤後傾型猫背』このタイプの猫背の方は骨盤が通常より後傾したことにより猫背になってしまったタイプです。最近ではこの猫背のタイプが非常に増えてきています。
このタイプの猫背の場合、お腹周りにお肉が付きやすくなったり下っ腹がポコっと出て幼児体系になりやすくなりますので、見た目的にもかなりマイナスになってしまいます。
この他にもいくつか猫背のタイプは有りますが、一般的にはこれら3つのタイプに分類されます。
また、これら猫背の種類により猫背の改善方法が異なるので、猫背改善体操や猫背改善ベルトを使用してもあまり効果は期待できません。
・自分の猫背のタイプを調べてみる
それでは実際に自分の猫背のタイプを調べてみる方法をお話したいと思います。
調べる方法は非常に簡単で、まず壁に足の踵を付け→お尻→背中→肩→頭と順番に壁に付けていきます。
この時、頭を壁に付けるのが窮屈な感じがするのならば猫背気味になります。
また、壁と腰の隙間が手のひら2枚分以上空いている場合は骨盤が過前湾気味なので骨盤前傾型猫背。逆に腰と壁の隙間が手のひら1枚も入らないと言う方は骨盤後傾型猫背となります。
・猫背になる原因
外反母趾や浮き指・扁平足があると、指がふんばれないため、重心がかかとに片寄ります。後ろへ倒れる危険性が増すため、本能的に背中を丸めたり、首を前に落としてバランスを保とうとします。これが、猫背の原因なのです。
もう一つの悪い姿勢は、背骨が曲がる「側弯症」です。 これも、病的なもの以外は足裏に隠れた原因があったのです。
外反母趾や浮き指・扁平足などの足裏のゆがみは、左右平等に起こりません。そのため、重心のかかと寄りにも、左右差が伴います。
この左右差を補うために、骨盤のゆがみと共に背骨にゆがみが起こるのです。
問題なことは、猫背や側弯症があると、背骨の上に首がバランスよく乗っていないため、重い頭を支える「首」に負担がかかり、首にズレやゆがみを起こします。
更に、外反母趾や浮き指・扁平足による不安定な足裏での歩行は、かかとからの過剰な衝撃やねじれを首に繰り返し伝えてしまうため、首の変形と共に、肩こり・首こり・頭痛・めまい・胃腸障害など様々な自律神経失調状態を引き起こしてしまうのです。
名古屋 猫背 姿勢
2016-04-18 [記事URL]
猫背とは背中が丸く曲がり顔が前に突き出した姿勢のことです。猫背というのは俗称であり医学的には「脊柱後湾症」といいます。
元々人の背骨は真っ直ぐなわけではなく、首から腰に掛けてS字を描くように曲がっています。
これは、体重の約10%と言われる頭の重さを支えるためでありS字を描くことで頭の重さを首・方・背中・腰に分散させているためです。
猫背になると頭の重さが首や肩に掛かるようになりひどい肩こりや頭痛に悩まされるようになります。また、常に背中が丸まっている状態なため内臓を圧迫し血行不良になり、胃腸の不調や手足がしびれたりすることもあります。他にも冷え性やむくみによって太りやすくなるなど症状は様々です。
猫背は脳梗塞やくも膜下出血など、恐ろしい症状を招く恐れもあります。これは、猫背になると首の骨の隙間にある椎骨動脈が圧迫された状態が続くためです。これによって、血管が破けたり詰まったりしやすくなり、脳梗塞やくも膜下出血のリスクが高まります。
猫背の認識は「背中が丸まっている」方が猫背だと認識するかと思いますが、実はこの背中の丸まる原因によって猫背の種類が分別されます。
今回は大きく3つのタイプに分けていきます。
1.そり腰により骨盤前傾型猫背タイプ
この猫背のタイプは骨盤が通常より過前湾している為、身体のバランスを取ろうとする際に首だけ前に出してしまい猫背の様な姿勢になります。また、腰が反り過ぎている為に腰痛にもなりやすい傾向があります。
2.一般的な猫背のタイプ
まず一般的に多い猫背タイプですが、背中の中央部分だけが丸まる「猫背」です。
背中にある姿勢を維持する筋肉が弱く常に背中を丸めるようになる為この様な姿勢になってしまいます。常にこの様な姿勢をしていると姿勢を維持する筋肉は普段から使わないことになるので余計筋力が低下します。仰向けで寝るのが辛くなりうつ伏せや横になって寝ることが多くなります。
3.骨盤後傾型猫背タイプ
最後は『骨盤後傾型猫背』このタイプの猫背の方は骨盤が通常より後傾したことにより猫背になってしまったタイプです。最近ではこの猫背のタイプが非常に増えてきています。
このタイプの猫背の場合、お腹周りにお肉が付きやすくなったり下っ腹がポコっと出て幼児体系になりやすくなります。見た目的にもあまり良くありません。
この他にもいくつか猫背のタイプは有りますが、一般的にはこれら3つのタイプに分類されます。
また、これら猫背の種類により猫背の改善方法が異なるので、猫背改善体操や猫背改善ベルトを使用してもあまり効果は期待できません。
・自分の猫背のタイプを調べてみる
それでは実際に自分の猫背のタイプを調べてみる方法を紹介します。
調べる方法は非常に簡単で、まず壁に足の踵を付け→お尻→背中→肩→頭と順番に壁に付けていきます。
この時、頭を壁に付けるのが窮屈な感じがするのならば猫背気味になります。
また、壁と腰の隙間が手のひら2枚分以上空いている場合は骨盤が過前湾気味なので骨盤前傾型猫背。逆に腰と壁の隙間が手のひら1枚も入らないと言う方は骨盤後傾型猫背となります。
・猫背になる原因
外反母趾や浮き指・扁平足があると、指がふんばれないため、重心がかかとに片寄ります。後ろへ倒れる危険性が増すため、本能的に背中を丸めたり、首を前に落としてバランスを保とうとします。これが、猫背の原因なのです。
もう一つの悪い姿勢は、背骨が曲がる「側弯症」です。 これも、病的なもの以外は足裏に隠れた原因があったのです。 外反母趾や浮き指・扁平足などの足裏のゆがみは、左右平等に起こりません。そのため、重心のかかと寄りにも、左右差が伴います。この左右差を補うために、骨盤のゆがみと共に背骨にゆがみが起こるのです。 問題なことは、猫背や側弯症があると、背骨の上に首がバランスよく乗っていないため、重い頭を支える「首」に負担がかかり、首にズレやゆがみを起こします。 更に、外反母趾や浮き指・扁平足による不安定な足裏での歩行は、かかとからの過剰な衝撃やねじれを首に繰り返し伝えてしまうため、首の変形と共に、肩こり・首こり・頭痛・めまい・胃腸障害など様々な自律神経失調状態を引き起こしてしまうのです。
ハイヒールをよく履いている女性に猫背が多いことをご存知ですか? ハイヒールを履くと、体の重心が前に傾むきます。その結果、前のめりな姿勢となり、猫背になってしまうのです。とくに、ハイヒールで長時間歩くという方は猫背になる原因となります。
普段仕事などで忙しい方でも簡単にできるストレッチ法を紹介します。
・通勤中にできる簡単なストレッチ
1.首をいつもより少し後ろに引く
2.両肩を後ろに引き肩甲骨を寄せる
3.スマートフォンを使うときは下を向かずに自分の目線より少し上で使う
・デスクワーク中にできるストレッチ
1.椅子に座った状態で背中を丸めたり背もたれを使って首・背中を反らすようにして伸ばす
2.両腕を体の後ろで組み肩甲骨を寄せるように組んだ腕を後ろに引く
3.肩を上下させる(肩を耳につけるように上げその後脱力する)
・寝る前にできる簡単なストレッチ
1.うつ伏せになった状態で体を反らす(えび反り)
2.両肘を曲げた状態で勢いよく後ろに引き上げる
3.ドアの枠を両端に手をかけて徐々に体を前に倒していく(胸や背中の筋肉が伸ばされる)
これらのストレッチを毎日継続することで猫背も改善されていくので毎日数分でも良いので習慣づけていきましょう。
また、デスクワーク中や運転中など座るときには可能なかぎり正しい姿勢を意識しましょう。
座るときの正しい姿勢とは...
1.顎を軽く引く
2.お尻を背もたれに付けるように腰掛ける
3.腰椎を立てるように背筋を伸ばす
4.両足が地面につくようにする
上記の4点を意識して正しい姿勢を習慣づけてください。
最後に猫背を治すには猫背強制ベルトなどは、一時的なものであまりおすすめはできません。
また、筋トレはある程度の筋肉は必要かもしれません。
筋トレさえすれば治るというものではなく、普段から正しい姿勢を意識することが猫背を治すための近道になります。
名古屋市南区 バレリユウー症状のむちうち
2016-04-12 [記事URL]
交通事故で最も多いむちうちは、首や肩周辺の組織にダメージが加わることで発生する症状です。
ただ、一般的にむちうちは、レントゲンやMRIで異常が確認できないことから、病院では、あまり親身になって治療をしてくれない事があります。
また、見た目に大きな怪我、病気ではないことから、「仮病」「大げさ」などと辛い言われ方をすることで精神的ダメージを受ける事も少なくありません。
体調の悪さをだれにも理解してもらえない辛さから、余計に病院の不親切さに不満やストレスを抱える事もあります。
その場合は、交通事故治療を専門とする接骨院等の治療も検討するといいでしょう。
現在、むちうちで悩んでいる方の多くが、柔道整復師が対応する接骨院等でむちうちの治療を受けています。
病院とは異なり、特別な器具や薬は一切使用せず、手技を中心としたオーダーメードの施術が特徴です。
【むちうちとは】
主に自動車の追突、衝突、急停車によって首に強い衝撃を受けて発症するのがむちうちです。
正式な疾病名は、頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頸部症候群などとなります。
頭痛や体のだるさ、疲労、吐き気、肩こりや背中の痛み、めまいなど、首の痛みに加え、あらゆる体調不良が発生します。
また交通事故以外にも、体と体を激しくぶつけ合うスポーツなどでもむちうちが起こります。
【むちうちの種類】
・頚椎捻挫タイプ
頚椎周辺の筋肉、じん帯などを損傷するむちうちで、むち打ち症の約8割がこのタイプです。
首の後ろや肩の痛みは、首の伸縮時に強くなり、肩周辺の動きが制限されます。
・根症状タイプ
頚椎のゆがみによって、神経が圧迫されることで症状が出現します。
首の痛み、腕の痛みや痺れ、疲労、倦怠感、後頭部の痛みや顔面麻痺などがあります。
せき、くしゃみ、首を曲げたり、まわすなどの行動で症状が悪化します。
・バレリユウー症状タイプ
後部交感神経症候群とも呼ばれるむちうちのタイプで、血流の低下によるめまい、頭痛、耳鳴り、吐き気が主な特徴です。
・脊髄症状タイプ
頚椎の脊柱管を通る脊髄や神経が損傷し、下肢の痺れや知覚異常が発生。
歩行障害や排便排尿障害に陥るケースもある。
・脳髄液減少タイプ
このタイプのむちうちによる症状は多彩で、不定愁訴のような症状が見られます。
初期に、頭痛をともない、症状が進行すると天気、気圧等によっても、痛みが強くなることがあります。
横になることで症状が治まる事もあります。
【お近くの交通事故治療専門院へ】
上記で紹介したむちうちの症状がはっきりとあるのに、レントゲン検査で、異常がないと診断されても治療を諦めてはいけません。
むちうちは、異常が見つけにくいのが一般的なので、交通事故治療を専門とする接骨院等による施術も視野に入れて改善に取り組みましょう。
現在、病院を通院している方でも並行して、接骨院等の施設に通うことは可能です。
1日でも早く症状が改善できるよう、また症状の悪化を防ぐためにも、納得いく方法で治療を受けるようにしてください。
名古屋市南区 バレリユウー症状のむちうちなら、「くろねこ腰痛整体院」にお任せください。
名古屋で首肩の痛みなら
2016-04-12 [記事URL]
肩こり・首の痛み
肩こりにもいくつか種類があります。今回は6つの原因に分けていきます。
1.筋肉疲労による肩こり
主な症状は肩が脹る・肩が重い・肩の上に鎧を載せられたよう・首から肩にかけてセメントで固められたようとも言われます。
この肩こりの原因は、筋肉の疲れや過緊張、負担がかかり過ぎる、筋肉の中での血行不良によることが多いです。また、夏の暑い時期に冷房の近くにいる、あるいは薄着をして首から肩の皮膚が見えるような服装をしていると、筋肉自体が冷やされます。すると、肩周辺の筋肉の中の血管が細くなって血行障害を起こし、筋肉が硬くなってしまうことから肩こりを訴える方もいます。
後頭部から鎖骨、肩甲骨周辺、さらには背中まである筋肉での問題や異常が、これらの症状を引き起こします。
2.頸の骨や周辺の血管・神経の問題による肩こり
主な症状は首全体が脹って締め付けられたような感じがする・頸から背中にかけての背骨も重苦しく感じる・横になっていれば楽なのに、起き上がると頸の骨にズンと重さを感じる頭痛を伴う肩こりがみられます。
背骨に問題があって起こる肩こりでは、「筋肉疲労による肩こり」で挙げたような肩の症状に加えて、以上のような症状が見られます。
ひどくなると肩や腕、あるいは手にかけて痺れるような感じや、物に触れても鈍く感じる、熱いものや冷たいものに触れても温度を感じない、あるいは手や指先、腕に力が入らない、場所によっては脚の痺れや動きがぎこちないなどの症状が現れたりします。
このような症状が出てくると重症ですので、すぐにでも整形外科を受診することをお勧めします。
3.ストレスによる肩こり
体や精神にストレスを受けると、肩こりになります。ストレスをうけると、筋肉を緊張させる交感神経の働きが活発になるからです。交感神経の働きが強くなると肩周辺の筋肉内の血管が収縮してしまい、血液循環が滞って、肩こりが起こります。
4.目の疲れによる肩こり
長時間の目の酷使により疲労が蓄積されて起こる症状を眼精疲労といいます。この眼精疲労が肩こりを招く場合があり、目の神経と体の筋肉は密接に関係していて、目の神経が疲労すると目や頭のまわりにある筋肉や首筋の筋肉が緊張して、血行不良となるからです。
5.歯のかみ合わせ不良、顎の関節の問題に由来する肩こり
主な症状は「筋肉疲労による肩こり」と同様、加えて首の前側でも脹った感じがする、口を大きく開けられない、口を開けると耳の前側で「カクッ」と音がする、口を開けると痛いなどがあります。
歯のかみ合わせが悪くて食べ物を噛むときに下顎の骨がずれたり、顎関節症などによって顎の痛みを感じる場合にも、肩こりが伴います。
その肩こりの症状や原因は、先の「筋肉の疲労などによる肩こり」とほぼ同じなのですが、顎関節周辺にも症状が伴ってきます。これらの顎周辺の症状は、耳の前側にある顎関節自体に問題がある場合と、食べ物を噛むときに使われる筋肉が異常に緊張していることに由来します。
また、下顎の骨を動かすときは、頸の周りの筋肉も一部役割を果たしているため、下顎の骨が動く咀嚼運動に問題があると、頸の筋肉にも影響が及びます。
6.頸部や胸にある臓器に問題があって起こる肩こり
主な症状鎖骨や肩甲骨周辺が何となく重だるい・マッサージをしてもあまり楽にならない・肩以外でも何かすっきりしないものを感じるなどがあります。
胸、正しくは胸郭や頸部にある臓器に問題がある場合でも、肩こりが見られる場合があります。その臓器とは、胸郭では主に心臓、肺、大動脈、頸部では甲状腺が挙げられます。
狭心症や心筋梗塞などの心臓病では一部の方で、特に左肩やその周辺から胸にかけての痛みを感じるようです。
ただ、心臓が酸欠を起こしていない状況では、肩に症状が出ないこともあり、肩こりとしては慢性的なものではないようです。
また、肺に病気のある方では、問題のある肺と同じ側の肩に症状が出てきます。この場合は、筋肉が脹るというよりは、何となく肩全体が重いと感じるようです。もちろん、肩以外の部分にも症状を伴うことがあります。
肩こりを予防するためには、肩を動かすことが大切です。肩の痛みやこりは、痛いからといって肩を動かさないでいると、筋肉や関節が硬くなりよりひどい状態になってしまいます。肩こりを防ぐには、まずからだを動かす意識を持つことから始めましょう。日頃から、正しい姿勢を心がけることも大切です。
ホームページをご覧のあなた様へのプレゼント!
キャンペーンのご案内
1日1名様限定 おひとり様1回限りで体験施術キャンペーンをご利用頂けます。
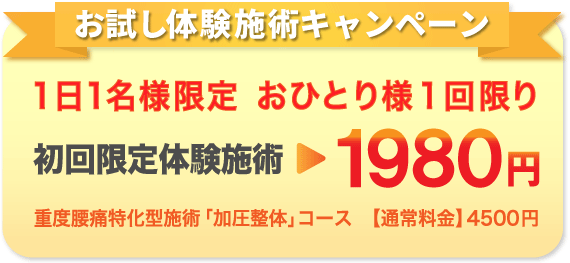
※重度の腰痛・ぎっくり腰・ヘルニア・坐骨神経痛の方が対象です。
お申し込みはこちら
電話・メール・LINEでのお問合せ
くろねこ腰痛整体院は、「完全予約制」となっておりますので、事前のご予約をお願い致します。

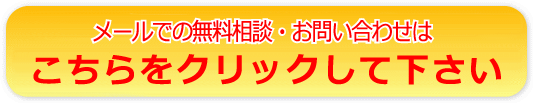
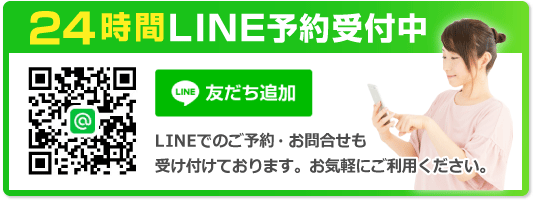
名古屋市南区「くろねこ腰痛整体院」へのお電話はこちら
| 住所 |
〒457-0862 名古屋市南区内田橋1丁目3-4 (スギ薬局内田橋店の目の前です) |
| 電話番号 |
090-1754-4466 (完全予約制) |
| 営業時間 |
9:00~23:00 (日曜日は17時まで)
|
| 定休日 |
不定休 |
| 最寄駅 |
地下鉄名城線「伝馬町駅」徒歩8分
名鉄常滑線「豊田本町駅」徒歩8分 |
| 駐車場 |
お客様専用駐車場3台有り |
PAGE TOP